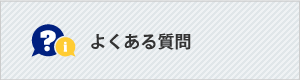本文
淡路島の食について学ぼう
印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月1日更新
淡路島の郷土料理
おだやかな気候の淡路島は、海の幸、山の幸に恵まれたすばらしいところです。食文化も先人の知恵を受け継いでおり、淡路島特有の食材や調理法で作られた郷土料理には、淡路島の暮らしや気候の特徴が現れています。農産物や海産物は、自然の影響を大きく受けることから、調理の技術や加工・保存を工夫して現在まで伝えられてきました。
時代が変わっても、農耕や人生の節目の行事として、また神社の祭りや地域の行事として、その土地の食べ物は大切にされています。
郷土料理…地元でとれた食材や地域独自の調理法をいかして、長い間受け継がれてきた料理
時代が変わっても、農耕や人生の節目の行事として、また神社の祭りや地域の行事として、その土地の食べ物は大切にされています。
郷土料理…地元でとれた食材や地域独自の調理法をいかして、長い間受け継がれてきた料理