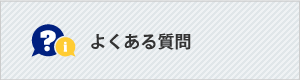本文
個人住民税とは
多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 納める税額 |
|---|---|
| 市内に住所のある人 | 均等割と所得割の合計額 |
| 市内に事務所、事業所または家屋敷のある人で、市内に住所のない人 | 均等割額 |
※市内に住所または事業所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
(例)令和5年10月に淡路市からA市に住所を移した人。
⇒令和5年度は淡路市が、令和6年度はA市が課税します。
扶養控除の対象となる所得金額
扶養控除の対象となるのは、所得金額が48万円以下の方です。(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。))
個人の住民税の非課税範囲について
以下の要件に該当される人は、個人の個人住民税が非課税です。非課税基準は税制改正等により変更される場合があります。
均等割・所得割とも非課税となる人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・前年中の合計所得が135万円(令和2年度以前は125万円)以下で次にあげる人
1.障害者 2.未成年 3.ひとり親、寡婦または寡夫
均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人は、均等割が非課税です。
◇本人のみ
38万円(令和2年度以前は28万円)
(給与収入のみの場合は収入金額が93万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が98万円以下の方。(ただし、
前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が148万円以下の方。))
◇控除対象配偶者または扶養親族がある人
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
令和2年度以前は28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円
所得割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人は、所得割が非課税です。
◇本人のみ
45万円(令和2年度以前は35万円)
(給与収入のみの場合は収入金額が100万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が105万円以下の方。(ただ
し、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が155万円以下の方。))
◇控除対象配偶者または扶養親族がある人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円
令和2年度以前は35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円
個人の住民税の非課税限度額について
住民税の非課税限度額についてまとめたものです。賦課期日現在の住所が淡路市以外の人、また、収入が2か所以上ある人は条件が異なりますのでご注意ください。
※社会保険上の扶養とは限度額が異なりますのでご注意ください。
|
区分 |
所得金額 |
条件 |
収入金額 |
|
障害者・未成年・ひとり親、寡婦、寡夫の人 |
135万円以下 |
給与収入のみ |
2,044,000円未満 |
|
障害者・未成年・ひとり親、寡婦、寡夫の人 |
135万円以下 |
公的年金のみで65才未満 |
2,166,667円以下 |
|
障害者・未成年・ひとり親、寡婦、寡夫の人 |
135万円以下 |
公的年金のみで65才以上 |
2,450,000円以下 |
|
扶養親族なしの人 |
38万円以下 |
給与収入のみ |
930,000円以下 |
|
扶養親族なしの人 |
38万円以下 |
公的年金のみで65才未満 |
980,000円以下 |
|
扶養親族なしの人 |
38万円以下 |
公的年金のみで65才以上 |
1,480,000円以下 |
|
所得税の非課税限度額 |
48万円以下 |
給与収入のみ |
1,030,000円以下 |