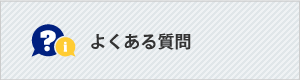本文
市営住宅制度のご案内
1 市営住宅とは
市営住宅は、住宅に困窮している方などのために、税金を使って建設した住宅であり、市民の貴重な財産です。そのため、民間の賃貸住宅とは違って、使用するに当たっては、様々な制限や注意しなければならないことがたくさんあります。したがって入居者の皆さんは、これらの「きまり」を守っていただき、住宅を大切に使用していただかなくてはなりません。
また、皆さんが楽しく気持ちよく生活できるかどうかは、入居者一人ひとりの心がけ次第です。お互いの協力によって、住みよい団地にしていただくようお願いします。
2 民間の賃貸住宅との違い
(1)入居には様々な条件の制限・制約があります。
- 入居者募集に応募される場合は、4に掲げる要件を満たす必要があります。
- 入居後は、市への届出や承認を得ないで同居者を増減することはできません。
- 入居名義人を承継する場合は、一定の条件・制限があります。
- 一定の収入を超えた方については、市営住宅を明け渡すよう努めていただきます。
(2)毎年、収入の状況に応じて家賃が決定(変動)されます。
毎年、入居する世帯全員の収入の申告をしていただくことが必要です(税の確定申告とは別の手続きです。)。この収入申告をしない場合は、近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)をいただくことになります。
収入の申告により1階層から8階層までの区分に応じた家賃が決定されます。
なお、収入超過者に対しては、割増賃料が加算され、その状態が続くと最終的には、民間住宅並みの家賃になります。
(3)修繕の程度は部屋ごとに異なります。
募集するお部屋は「お住まいいただく上で支障がないか」という点を基準として、修繕をします。そのため、生活される上で支障のない汚れや傷、破損などはそのままにしますので、美観はお部屋によって異なります。
なお、募集したお部屋の内覧は行っておりませんので、ご了承ください。
3 市営住宅の入居者募集
(1)市営住宅の入居者募集は、原則年5回、6月、8月、10月、12月、2月に実施しています。
入居が可能となる日は募集月の翌月以降となります。
受付期間や募集住宅、募集の方法については、募集月に以下の方法でご案内しています(募集期間外でのご案内は原則できません。)。
(2)月初めに淡路市内の新聞への折込みチラシ及び淡路市ホームページへ掲載します。
なお、都市計画課及び各事務所の窓口にて、募集住宅の一覧と入居申込案内書を配布しています。
4 市営住宅の入居資格
市営住宅に入居するためには、次の(1)~(6)すべてに該当することが必要です。
(1)現に同居し、または同居しようとする親族のある方
内縁関係にある方や婚約者のいる方も申し込みができます。
- 内縁関係にある方は、戸籍謄本等で他に婚姻関係が無いこと、また、住民票で内縁関係を確認させていただきます。
- 婚約者のいる方は、入居許可日から3か月以内に入籍できる方を条件とし、後日、戸籍謄本を提出していただきます。
- 家族構成が夫婦または親子を主とし、入居される方が原則として2人以上であること(友人などの寄り合い世帯、兄弟、姉妹のみの世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟または姉妹を呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については、申し込みはできません。)。
次のいずれかに該当する方は、単身でも申し込みができます。
戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認でき、次のいずれかに該当する方(なお、申し込みできる住宅は募集住宅一覧の「単」と表示された住宅に限ります。)
- 入居申込受付時に満60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受け1級から4級までの障害のある方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方
- 療育手帳の交付を受け「A」から「B2」の方
- 政令で定める特殊の疾病により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける18歳以上の者その他これに類する者として市長が別に定める方
- 「生活保護法」第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等で支援給付を受けている方
- 戦傷病手帳の交付を受け、「恩給法」の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
- 「配偶者暴力防止等法」第3条第3項第3号の規定による一時保護、または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 「配偶者暴力防止等法」第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、この命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
- 「犯罪被害者等基本法」第2条第1項に規定する犯罪等により現に居住する住宅に引き続き居住することが困難となったことが明らかである方
- その他(海外からの引揚者(大臣証明)で本邦に引き揚げた日から起算して5年未満、原子爆弾被爆者の認定者、法に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方)
※ 上記1~10のいずれかに該当する方であっても、「常時介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができずまたは受けることが困難と認められる方」は申し込みできません。
(2)現在、住宅に困っている方
- 現在、公営住宅に入居し、または入居決定されている方は、申し込みができません(市営住宅の交換実施要綱該当者は除く)。
- 民間賃貸住宅等に居住し、家賃の不払い等により住宅の立退きを求められている方は、申し込みができません。
- 持家の方は、入居時までに契約書等により、持家を処分することを証明できる方でないと申し込みができません。
(3)市税を滞納していない方
(4)収入基準を満たす方[所得月額が158,000円以下の方(裁量階層世帯は214,000円以下)]
(5)本人または同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
(6)連帯保証人(2人)を立てられる方
5 収入基準について
6 裁量階層世帯とは?
|
該当世帯区分 |
該当要件 |
政令月額 |
|
|---|---|---|---|
|
(1) 新婚世帯 |
合計年齢が80歳未満で婚姻成立後2年以内の世帯(婚約・内縁関係含む) |
214,000円 |
|
|
(2) 子育て世帯 |
同居者に中学校を修了するまでの子供がいる世帯 |
||
|
(3) 高齢者世帯 |
次のいずれかに該当する世帯 ア 単身で申し込み本人が満60歳以上 イ 申し込み本人が満60歳以上で、かつ、同居親族のいずれもが満60歳以上または満18歳未満の場合 |
||
|
(4) 障害者世帯 |
入居する方の中に次のアからエに該当する方がいる世帯 ア 身体障害者手帳1~4級の方 イ 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方 ウ 療育手帳「A」または「B1」判定の方 エ 障害基礎(国民)年金及び障害厚生年金の1~2級の障害のある方 |
||
|
(5)戦傷病者世帯 |
入居する方の中に戦傷病者手帳の交付を受け、「恩給法」の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症に該当する方がいる世帯 |
||
|
(6) 被爆者世帯 |
入居する方の中に「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
||
|
(7) 引揚者世帯 |
入居する方の中に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方がいる世帯 |
||
|
(8) ハンセン病療養所入居者等世帯 |
入居する方の中に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所等に該当する方がいる世帯 |
||
| (9) 特定疾患傷病者世帯 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける方で18歳以上である者その他これ類する者として市長が別に定める方 | ||
|
(10) 犯罪被害者等世帯 |
「犯罪被害者等基本法」第2条第1項に規定する犯罪等により、現に居住する住宅に引き続き居住することが困難となったことが明らかである方がいる世帯 |
||
7 市営住宅の使用料について
8 入居予定者の選考方法
(1)公開抽選
なお、募集締切時点で他に申込者がない住宅については、締切後に当選の連絡をさせていただきます。
(2)当選者、次点者
当選者の中から、辞退者、失格者が生じた場合に備えて、あらかじめ抽選時に次点者を決定します。
(3)請書の提出
- 指定された日までに請書を提出していただきます。請書には、連帯保証人(2名)の署名、押印が必要です。
- 申請者は、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
- 連帯保証人は、実印の押印のほか、印鑑証明書、納税証明書、所得証明書の添付が必要です。
- 連帯保証人となれるのは、次の資格すべてを有する方です。
- 市内に居住するものであること(市営住宅入居者を除く。)。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
- 独立の生計を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
(4)敷金の納入及び入居許可、鍵の引渡し
入居許可日から10日以内に入居し、入居後すみやかに住所登録の届出をしていただきます。